体が疲れやすい原因を知って、疲れにくい体を手に入れたいと思いませんか?
最近、疲れやすいので、何とかしたい場合には、
 何もしていないのに疲れやすい…
何もしていないのに疲れやすい… いつも体が重たい、だるい、フラフラする…
いつも体が重たい、だるい、フラフラする… 1日中眠い、寝起きが辛い、起きれない…
1日中眠い、寝起きが辛い、起きれない… 十分な睡眠時間をとっても疲れが取れない…
十分な睡眠時間をとっても疲れが取れない… 体が疲れやすい原因・疲れが取れない原因が知りたい…
体が疲れやすい原因・疲れが取れない原因が知りたい… 肝臓、糖尿病、貧血などの病気が原因かも…?
肝臓、糖尿病、貧血などの病気が原因かも…? すぐ疲れるので、疲れにくい体に体質改善したい…!
すぐ疲れるので、疲れにくい体に体質改善したい…! 疲れやすい体質を改善する方法が知りたい…
疲れやすい体質を改善する方法が知りたい…
と言った様に、体が疲れやすいと言うことで、「家に帰るころにはクタクタになっている」、「最近、疲れやすくなった」と言った人は、ここで紹介している「疲れが取れない体の対策」や「疲れがとれる生活習慣の改善方法」が参考になると思います。
ここでは、基本的に、疲れやすい原因を紹介しつつ、改善する方法としては、どういった事を実践すると良いのか?と言った点を、出来るだけ多くの情報を集めて紹介しています。
あなたに合った、役に立つ体が疲れやすい原因の対策、改善方法があれば幸いです。

疲れやすい原因と改善方法に関する情報を出来るだけ多く集めました。
掲載情報が多いので、下記の目次から気になる項目にジャンプしてチェックすると便利です。

最近、「疲れやすい」と言った症状に悩まされていませんか?

- 「特に、疲れる事をしていないのに、疲れやすい。。。」
- 「最近、疲れやすくなって、体がだるい。。」
- 「いつも体が重たく感じる。。。」
- 「首や背中、腰がガチガチに凝っている。。。」
- 「頭痛や耳鳴り、頭がボーっとする。
- 「いくら寝ても、寝たりない。。。」
- 「朝起きても目覚めが悪い。。。」
- 「朝、布団から起き上がれないぐらいしんどい。。。」
- 「朝はしんどく、午前中が台無しになる。。。」
以前に比べて疲れやすい人は、原因をキチンと調べておくと、思いがけずに簡単に改善したり、または、病気で、早く病院に行って治療しないと改善が難しいケースもあるので、早めのチェックしておくのがオススメです。
基本的な疲れやすくなる原因とは?
体が疲れやすい体質になる原因には、色々な原因があります。
基本的な疲れやすい原因、症状としては、
- 加齢による体力の低下
- 生活習慣が不規則
- 自律神経の乱れ
- 更年期障害
- 思いがけない病気
依然と比べると、体が疲れやすくなった場合には、まずは、年齢の経過で、体が老化して体力が落ちる場合があります。しかし、人によっては、10代でも疲れやすくなった、という人もいます。
疲れやすい体質になると、「体がだるい」、「体がしんどい」と言った以外にも「1日中眠い」、「体が重い」、「肩こり」、「食欲不振」などの様々な症状が現れます。
体力低下以外にも、生活習慣や食事、ストレスなど様々な原因があります。あなたは、何が原因で、疲れやすいのか?下記から順に紹介するので参考にしてください。
体が疲れやすい原因&改善方法
体が疲れやすい原因には、栄養不足、精神披露、ストレス、体力低下、睡眠不足、生活習慣の乱れ、自律神経の乱れなど色々な原因があります。
ここでは、実際に、疲れやすい原因と改善方法としては、
- ①ストレス
- ②考え方のクセによる精神的な疲労
- ③身体的な疲労や運動のやりすぎ
- ④運動不足
- ⑤加齢
- ⑥栄養不足
- ⑦食事の偏り
- ⑧食欲不振や体調不良
- ⑨水分不足
- ⑩睡眠不足や質
- ⑪自律神経失調症・自律神経の乱れ
- ⑫生活の乱れ・不規則な生活
- ⑬肝臓の疲れ
- ⑭貧血
- ⑮更年期障害
- ⑯妊娠
- ⑰子供が疲れやすい
以上のような、疲れやすい原因とその対処方法を、順番に紹介します。
①ストレスが原因&改善方法
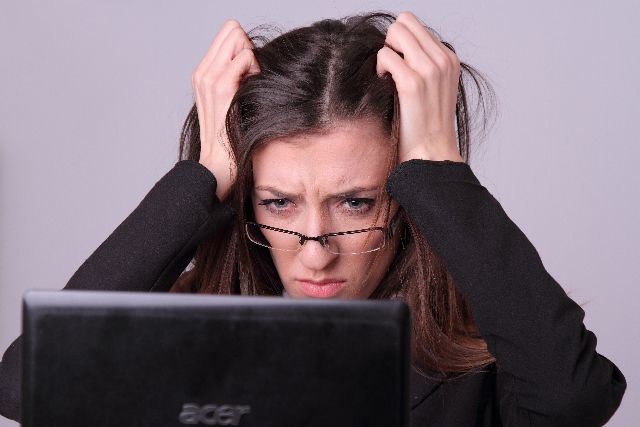
ストレスが溜まっている人というのは、疲れやすくなる可能性があるので注意が必要です。
具体的なストレスの原因になる事例というのは、
- 長時間の仕事や仕事のノルマ、過労
- 職場や家庭、友達、子供の学校の人間関係
- 不規則な食生活・栄養不足
- 睡眠不足や眠れないなどの不眠症
- 空気中の化学物質
- 食品に含まれている食品添加物
- 洗剤や芳香剤に含まれる界面活性剤
- 精神的なプレッシャー、緊張が強いられる環境
- 女性は、出産、更年期
- 長時間、同じ姿勢をしている
- 仕事、家事、育児、介護などのストレス
- 花粉、猛暑、テレビ、ゲーム、ブルーライトなど
上記の様なケースで、ストレスを感じる人が多いのではないかと思います。
これらのストレスは、大きく分類すると「身体的な疲労」、「精神的疲労」と言った様な種類に分けることが出来ます。
このようなストレスを感じる生活環境が続くと、疲れやすい原因になります。ストレスを感じる時間が長く続くと、疲れやすい、疲れが取れない、眠れない、だるいなどの症状が出る可能性があります。
強いストレスを感じるとどうなるか?
人間は、強いストレスを感じると、ストレスホルモンが副腎から分泌されて、自律神経やホルモンバランスなどに影響して「心」や「体」を守ろうとします。
しかし、強いストレスを継続して感じていると、副腎が疲労して、ストレスホルモンの分泌が十分に出来なくなり慢性疲労を起こす原因になります。
さらに、その結果、自律神経が乱れて、交感神経と副交感神経のバランスが狂い、身体のバランスが崩れて、疲れやすい体質になってしまいます。
交感神経とは?
交感神経は、通常、昼間に優位になる自律神経です。特に、交感神経は、ストレスや緊張を感じたときに優位に働くことで、筋肉に血液を多く流し、急な変化に反応して、素早く行動できようにします。
いつでも動けるように準備しているので、体が準備しているので、交感神経が優位な状態が継続すると、筋肉が硬くなり緊張する状態が継続する事になるので、「肩がこる」、「首がこる」、「体がガチガチ」、「体が重たい」と言った疲労感を感じやすく、溜まりやすくなります。
この為、普段の生活で、仕事や人間関係、過労などによって、多くストレスを感じると「交感神経」が働く優位な時間が長くなり、疲労が溜まりやすくなります。
副交感神経とは?
副交感神経とは、寝ている時やリラックスしている時、ゆったりと落ち着いている時に優位に働く自律神経です。
この副交感神経が働くことで、神経をリラックスさせて、昼間に受けた体へのダメージを夜、寝ている時に修復して、元気に戻す働きがあります。
副交感神経の働きがストレス対策にも大切!
ストレス対策には、副交感神経が大切な役割を担っています。
副交感神経が優位になり、活発に働くようになると、
- 筋肉がゆるむ
- 血管が広がり血流が良くなる
- 心拍がゆっくりになる
- リンパの流れが良くなる
- 内臓が活発になる
- 成長ホルモンが分泌される
- 細胞の代謝がよくなる
血液の流れが良くなると、酸素や栄養が全身の細胞に送られます。また、リンパの流れが良くなると老廃物や疲労物質を排出することができます。
交感神経と副交感神経のバランスとは?
昼間には、ストレスや緊張、活動の為に交感神経が優位になり、体が活動しやすくなります。しかし、その分、体に疲労がたまりやすくなります。
これに対して、夜など、寝ている時やリラックスしている時には、副交感神経が優位になります。副交感神経が優位になりリラックスして眠っている時には、疲労の回復、体の修復などが行われます。
この自律神経である交感神経と副交感神経のバランスが取れていれば問題ありませんが、強いストレスを長い時間、受け続けると、交感神経が強く働く時間が多くなり、自律神経のバランスが崩れて、疲れやすい体質になる原因になります。
自律神経のバランスが崩れるとどうなるか?
自律神経の「交感神経」と「副交感神経」のバランスが崩れると、どうなるのでしょうか?
具体的に、自律神経のバランスが崩れると、
- 夜に交感神経が活発になり、眠れなくなる
- 体が緊張している状態が長く続いて身体的な疲労が取りにくくなる
- リラックスしにくくなる
この為、自律神経のバランスが崩れると、疲れやすい体、疲れが取れない体になる事があります。
ストレス解消で、自律神経のバランスを整える
強いストレスを継続的に感じていると、自律神経のバランスが崩れて、交感神経が優位になるので、疲れやすい体質になる可能性があります。
この為、自律神経のバランスを整える為のストレス解消法としては、
- ストレス解消の習慣を持つ
- ウォーキングや軽いジョギングなどの運動習慣
- 趣味のスポーツをする
- 半身浴や温泉などでリラックス
- マッサージやリンパマッサージ、ヨガなどを行う
- 映画や読書、音楽を楽しむ
- 没頭できる趣味を持つ
以上の通り、自分なりに、趣味や運動で、ストレス解消の生活習慣を持つ事で、自律神経のバランスを取って、副交感神経を優位にして、疲れやすい体質改善をする習慣を意識して持つ必要があります。
特に、ウォーキングや軽いジョギングなどの運動習慣は、ストレス解消と共に、体を疲れさせる事で、夜、睡眠がシッカリと取ることで、疲れやすい生活習慣を改善する効果が期待できます。
②考え方のクセによる精神的な疲労が原因&改善方法

生活習慣だけではなく、考え方のクセが精神的な疲労したり、疲れによって悪い考え方になる場合、疲れやすい原因になっている場合があります。
具体的な疲れやすい考え方のクセとしては、
- 責任感が強い
- 完璧主義
- 理想を追求する
- 感情の処理能力が弱い
- パニックを起こす
- 集中力にかける
- 疲れやすい無気力
- イライラしやすい
- 前向きになれない
- ネガティブ思考で不安症
- 自律神経が乱れやすい
- 取り越し苦労が多い
- 自信喪失、自虐的な思考
- 脳の緊張や神経疲労
基本的には、精神的に、完璧を求めたり、イライラしやすい、自分に自信が無い、不安であると言った様なパターンで、ストレスを感じやすい考え方のクセを持っている人が、ストレスを溜める事で、疲れやすい原因になるケースがあります。
責任感が強く、完璧主義者の考え方のクセ
責任感が強く、完璧主義者であったり、理想を追っている人は、自分が行った事に満足できずに、自分を肯定できないので、満足を感じることが出来ないので、それがストレスになるケースがあります。
感情が不安定、イライラする、パニックを起こす考え方のクセ
感情が不安定な人で、イライラしたり、パニックを起こすような感情の処理が苦手な人は、精神的に不安定になり、起きた物事に対して、精神的に不安定になるので、ストレスが溜まりやすいです。
ネガティブ思考で、自信喪失、自己否定的な考え方のクセ
前向きになれないで、ネガティブで、自己否定するような考え方の人は、何をしても不安を感じてストレスが溜まりやすくなります。
以上の通り、考え方が、完璧主義者や感情的に不安定、ネガティブ思考と言った様な精神的に偏りがある人は、それがストレスになり、自律神経のバランスを崩すことで、疲れやすい体質、習慣になっている可能性があります。
③身体的な疲労や運動のやりすぎが原因&改善方法

疲れやすい時というのは、運動のやりすぎによって、身体的に疲労が蓄積しているケースがあります。
例えば、過剰な運動をすると、身体的、肉体的な疲労が溜まると、
- 筋肉を動かす為のエネルギーが不足
- 疲労物質が肉体に蓄積される
以上のような事が原因で、身体的な疲労を感じて疲れやすい状態になる場合があります。
筋肉を動かす為のエネルギーが不足
筋肉を動かすエネルギーが不足すると、疲労物質が蓄積しやすくなります。筋肉もエネルギー不足の状態が続くと、チカラを発揮する事が出来ずに疲れてしまう場合があります。
具体的には、体のエネルギーとしては、ビタミンB1やビタミンB6、ミネラルなどが不足すると疲れやすくなる可能性があります。
疲労物質が肉体に蓄積される
疲労物質が肉体に蓄積されると、筋肉の張りとなって、体に疲れやすさを感じる原因になります。
④運動不足が原因&改善方法

運動不足によって、疲れやすい体質になっている可能性があります。
具体的に、運動不足が疲れやすい原因としては、
- 筋肉低下で体力不足で疲れやすくなる
- 運動不足で肥満になり、体重増加
- 成長ホルモンの分泌量の低下
- 細胞内の機能が低下する
- 血流が悪くなる
上記の様な事が原因で、運動不足が原因で、疲れやすい体質になる可能性があります。
筋肉量の低下、体力不足
運動不足の人は、筋肉量の低下や体力不足によって、ちょっとした運動で、疲労を感じやすくなり、疲れやすい体質になります。
成長ホルモンの分泌、細胞内の機能の低下
運動不足で代謝が悪くなると、成長ホルモンの分泌や細胞内の機能が低下します。成長ホルモンや細胞内の機能は、体の細胞の再生にも必要です。代謝が悪くなり、細胞の再生が悪くなると疲れやすくなる可能性があります。
血流が悪くなる
適度な運動習慣がある人は、血行が良くなり血流が良くなります。血液は、全身の細胞に酸素や栄養を送るのに必要です。運動不足で、血流が悪くなると、全身の細胞への酸素や栄養が不足して、疲れやすい状態になってしまいます。
⑤加齢が原因&改善方法

20代よりも30代、30代よりも40代、50代と言った様に、年齢の経過とともに疲れを感じる人は多いと思います。ここでは、疲れやすい原因として、加齢について紹介します。
具体的に加齢による体力低下で疲れやすくなる理由としては、
- 加齢によって筋肉量が低下する
- 体内の老廃物が蓄積されやすくなる
- 加齢でビタミンB1の吸収量、体内保持力の低下
- 生理機能の低下による栄養を腸から吸収する能力の低下
体が老化すると上記のような事が原因で疲れを感じやすくなります。
加齢によって筋肉量が低下する
年齢の経過とともに、身体の筋肉量が低下すると、若い時と比較すると疲れやすい体質になることがあります。筋肉量が低下する事で、ちょっとして日常的な動作でも疲れやすくなるケースがあります。
特に年齢の経過と共に、疲れを感じやすくなったら、運動や筋トレを習慣にして体力をつけると良いです。
体内の老廃物が蓄積されやすくなる
体内に溜まった老廃物は、通常、体外に排泄されます。しかし、加齢によって代謝が悪くなると、体内の老廃物が蓄積されて排泄がスムーズに行われずに疲れやすくなる可能性があります。
この為、運動や栄養補充で、代謝を良くして、体内の老廃物を効率的に排出する必要があります。
加齢でビタミンB1の吸収量、体内保持力の低下
加齢によってビタミンB1の吸収率が悪くなり、また、体内で保持できる分量が低下すると、筋肉や神経の活動に必要なエネルギーが不足することで、疲れやすい体質になっているケースがあります。
生理機能の低下による栄養を腸から吸収する能力の低下
加齢によって、身体の生理機能が低下すると、栄養が腸から十分に吸収できなくなると、食事で取った栄養が十分に吸収できずに栄養不足で、疲れやすい体質になる可能性がります。
⑥栄養不足が原因&改善方法

栄養が不足すると肉体的に必要なエネルギーが不足するので、肉体的疲労によって、疲れやすい原因になる事があります。
基本的に、人間は、毎日、30種類の品目を食事で取っている事が理想だと言われていますが、実際には、そんな人は、少ないと思います。人間は、食べたモノで体を作っているので、食べ物からのビタミンが不足すると、体調が悪くなる事があります。
特に、身体の疲労や疲れを感じやすい人は、ビタミンB群、ビタミンCが必要です。
ビタミンBの不足と疲れの関係
ビタミンBとは、ビタミンB1、ビオチン、ナイアシンなどの ビタミンB群のことです。このビタミンBは、体内でのエネルギー代謝に必要な栄養です。
もしも、ビタミンBが不足すると代謝が悪くなり、疲れやすくなったり、食欲不振と言った症状が起こる可能性があります。
ビタミンCの不足と疲れの関係
ビタミンCは、抗酸化物質としても知られています。さらに、ビタミンCは、ストレスを感じたときに、副腎の働きを強化する効果が期待できます。その結果、抗ストレスホルモンの分泌が促進されて、筋肉中に溜まっている疲労物質を、より早く分解して取り除く効果が期待できます。
もしも、最近、疲れやすいと感じた場合には、ビタミンB群やビタミンCを意識的に摂取すると良いです。
⑦食事の偏りが原因&改善方法

毎日の食事に偏りがある場合には、食事の偏りが原因で疲れやすい原因になる可能性もあります。
具体的な食事の偏りで、疲れやすい体質になる原因としては、
- 食事の偏りで、ビタミンやミネラルが不足する
- 毎日、外食やコンビニ弁当で、栄養バランスの偏り
- 食べる量が少なく、十分な量の栄養が取れていない
- 過剰なダイエットで栄養不足
- 食事を過剰に摂り過ぎている
上記のように、食事での栄養バランスの偏り、食事量が少ない、過剰ダイエットなどによって、特に、ビタミン、ミネラルが不足すると、疲れやすい体質になるので注意が必要です。
食事の偏りで、ビタミンやミネラルが不足する
ビタミン、ミネラルは、体内の代謝に必要な栄養成分です。もしも、ビタミンやミネラルが不足すると、代謝が落ちて、活動するのに必要なエネルギーが作れずに、疲れやすい体質になるケースがあります。
例えば、食事での栄養不足として、ビタミンB1が不足している場合には、体内での糖質の代謝が悪くなり、疲労物質の乳酸などが蓄積して、疲れやすくなり、体がだるい、疲れやすいなどの症状が合わられる事があります。
毎日、外食やコンビニ弁当で、栄養バランスの偏り
毎日の食事が、外食やコンビニ弁当などが多い場合には、いつも同じようなモノを食べていると栄養のバランスが崩れる可能性があります。そうすると、体内での疲労回復、エネルギーの生成などに必要な栄養が不足して、疲れやすい体質になる事があります。
食べる量が少なく、十分な量の栄養が取れていない
食事量が少ない人の場合には、十分な量の栄養が取れていない事で、疲労回復に必要な栄養が足りずに、体力が付かずに疲れやすい体質になるケースがあります。
過剰なダイエットで栄養不足
過剰なダイエットをして、朝食を抜いて、昼食を軽く済ませていると、食事で必要な栄養やエネルギーが取れていない場合には、ビタミン類やミネラルなどの栄養が不足しがちです。
食事を過剰に摂り過ぎている
食事をシッカリととれば、栄養が十分に補充できるので、疲れにも良いと思うかもしれません。しかし、お腹いっぱいになるぐらい、満腹になるまで食べていると、胃腸に負担がかかるので、逆に疲れやすくなるので注意が必要です。
特に、寝る前に食事を摂るのは疲れやすい体質の人は注意が必要です。通常、睡眠時は、体の細胞の修復や疲労の回復が行われます。しかし、寝る前に食事を食べると、睡眠中に胃腸で消化が行われるので、体の疲労回復が遅れるので、朝になっても疲労が残る可能性があります。
⑧食欲不振や体調不良が原因&改善方法

食欲不振になると、自律神経が乱れて、免疫力の低下を引き起こす事で、風邪をひく、胃腸の不具合、頭痛、冷え、貧血などの体調不良になることがあります。
このように、食欲不振や体調不良により、疲労を感じることで、疲れやすい体質になっている可能性があります。
何かしら病気である場合は、病院に行って医師の診察を受けて、適切な処置を行う必要があります。もしも、病気でない場合には、生活習慣の乱れで、自律神経の乱れが原因の可能性があります。
⑨水分不足が原因&改善方法

人間の肉体は、半分以上が水分で出来ています。
この人間の体内の水分量は、
- 子供:約70%
- 成人:約60%
- 老人:約50%
このように、人間の体内にある水分量が低下すると、細胞内が衰えて老化が進みます。
水分不足と疲労の関係
もしも、水分不足で、体内に十分な水分が無い場合には、様々な悪影響をお越し疲れやすくなります。
具体的な水分不足で疲労を起こす原因としては、
- 血流が悪くなる
- 代謝が落ちる
- 毒素の排出が悪くなる
以上の様に、十分な水分補給が出来ない場合には、体調不良から疲れやすい体質になる可能性があります。具体的には、下記で紹介します。
血流が悪くなる
水分不足で血流が悪くなる理由は、水分が少なくなることから、血液がどろどろになって、血の流れが悪くなるからです。この為、全身に、血液がスムーズに送りにくくなり、全身の細胞に酸素や栄養を送りにくくなり、疲労がたまりやすくなります。
もしも、水分を補う事が出来れば、血液に十分な水分が補われると心臓が効率的に血液を送ることで、全身に酸素や栄養を運びやすくなります。
代謝が落ちる
水分不足で、全身の細胞の水分が少なくなると、代謝が正常に行えなくなり、組織が壊れ始めます。また、血液の老が減って、低血圧症になって、体調不良から疲れやすくなる可能性があります。
毒素の排出が悪くなる
水分が十分に摂っていると、腎臓を良好な状態にして毒素を排出する事ができます。しかし、水分が不足すると、腎臓が思うように毒素の排出が出来なくなり、体調不良の原因になる事があります。
⑩睡眠不足や質が原因&改善方法

疲れやすい体質として、睡眠不足や睡眠の質が悪いのが原因の場合があります。
どのような睡眠が疲れやすい体質の原因になるかと言うと、
- 睡眠不足
- 睡眠の質
睡眠不足や睡眠の質について、疲れやすい体質との関係の詳細は、下記で個別に紹介しておきます。
睡眠不足が疲労、ストレスが原因
睡眠不足は、身体的に大きなストレスや疲労になります。特に寝不足になるのは、単純に睡眠時間が短い、睡眠時間が毎日バラバラ、昼夜が逆転していると言った人は、寝不足になり、体調不良や疲労の原因になるケースがあります。
実際に、人が寝ている時は、睡眠中の体内では、
- 睡眠中に脳や身体を休める
- 成長ホルモンを分泌して細胞を活性化する
- 食べ物を消化して栄養を蓄える
この為、睡眠不足が続くと、上記のような事が十分に行われないので、疲れやすい体調になる可能性があります。
睡眠の質の低下と疲れやすい体質の関係
睡眠時間を十分に確保するのも大切ですが、それと同じく必要なのが睡眠の質を向上させる事です。
もしも、睡眠の質が悪い場合の体に対する影響としては、
- 朝起きた直後に疲労感がある
- 脳の疲れが残る
- 精神的な安定やストレスが残る
- 成長ホルモンの分泌に影響する
- 細胞分裂による疲労の回復が不十分
- 筋肉や肌の修復、再生が不十分
- 副交感神経の働きに関係する
睡眠不足であったり、睡眠の質が低下すると、まずは、朝、寝起きが悪くなり、疲労感が残ったり、脳が付かれている状態があります。
精神的な安定やストレスが残る
睡眠不足、睡眠の質が悪い場合には、寝不足な状態だと、どうしてもストレスになる事があります。
成長ホルモンの分泌に影響する
人間は、眠っている間に、成長ホルモンが分泌されます。この成長ホルモンによって、お肌や髪、その他の体の部分が細胞分裂を行い、修復が行われます。睡眠不足や睡眠の質が悪いと、成長ホルモンの分泌量が減り、体の回復に影響する可能性があります。
細胞分裂による疲労の回復が不十分
睡眠の質が低下すると、睡眠中の成長ホルモンの分泌が悪くなるので、体内の細胞分裂に影響して、疲労の回復にも影響します。
筋肉や肌の修復、再生が不十分
筋肉や肌の修復は、睡眠中に成長ホルモンの分泌が促進されて行われます。この為、睡眠の質が悪くなると、成長ホルモンの分泌が悪くなると、筋肉や肌の修復が効率的に行えなくなる場合があります。
⑪自律神経失調症・自律神経の乱れが原因&改善方法

自律神経が乱れると、交感神経と副交感神経のバランスが悪くなるので、脳が緊張しているじちで、交感神経の働きが優位な状態が継続し、内臓、筋肉が働き続けることで、身体の疲れがたまってしまいます。
このような肉体疲労、精神的疲労、神経疲労のような疲労が続くと、自律神経の乱れが長く続いていると、自律神経失調症と言った様な症状にまでなるケースがあります。
自律神経が乱れると、体をリラックスさせて、疲労回復、細胞の修復を行う為の副交感神経が十分に働けなくなることで、疲れやすい体質になるので注意が必要です。
⑫生活の乱れ・不規則な生活が原因&改善方法

疲れやすい人の体の疲れが一番溜まる原因となっているのは、「不規則な生活」、「生活習慣の乱れ」です。
特に、疲れが溜まりやすい生活の乱れとしては、
- 夜更かしをする
- 昼夜が逆転している
- 睡眠時間が毎日定まっていない
- 寝不足で十分な睡眠時間がとれない
特に、睡眠不足、眠りの質が浅い場合には、脳が十分に休まらずに、食べ物の消化、成長ホルモンの分泌も少なくなり、体や脳の回復が十分に行えなくなり、疲労が溜まる傾向が出てきます。
また、食欲を増進させるグレリンホルモンが増えて、満腹感を感じるレプチンというホルモンが減るので、食べ過ぎによる肥満になって、疲れやすい体になりやすくなります。
生活習慣を正して、疲れやすい体質を改善する
睡眠不足や眠りの質が浅い人は、まずは、決まった時間に寝て、起きる生活習慣を持つ必要があります。また、睡眠時間は、8時間前後、と言った十分な時間を確保するのが理想的だと言われています。
疲れやすい体質を改善したい場合には、規則正しい生活で、睡眠時間と睡眠の質を確保しつつ、ストレス解消をする生活に見直す必要があります。
やストレスは、疲れやすい体を作ってしまいますので、規則正しい生活と、ストレス解消法を見つけるようにしましょう。
⑬肝臓の疲れが原因&改善方法

十分な睡眠をとっているつもりでも、飲酒やタバコなどで肝臓が疲れきって、機能が低下している場合には、疲れやすい体になってしまいます。
実際に、肝臓の疲れの原因となる事としては、
- 飲み過ぎ
- 食べ過ぎ
- ストレスが溜まっている
- タバコの喫煙
- 睡眠不足
- 過剰な運動
- 薬やサプリを飲んでいる
- 食品添加物の多いモノを食べている
- 高タンパク質、高脂質の食事
- 運動不足で脂肪に栄養が溜まる
上記のような飲酒、食べ個、薬、食品添加物は、肝臓で解毒が頻繁に行われると、肝臓が疲れて披露し、働きが悪くなります。また、運動不足や高タンパク質、高脂質な食事で、肝臓に栄養が溜まり脂肪肝になり、働きが弱まります。
このように、肝臓の働きが弱ると解毒が十分に行えずに、疲れやすい体質になります。
⑭貧血が原因&改善方法

貧血の人というのは、「体が疲れやすい」と言った症状が出る場合があります。貧血になると、血液で全身の細胞に酸素や栄養が十分に送ることが出来ません。
具体的に、貧血になった時の症状としては、
- 全身の細胞に酸素が十分に送れない
- 酸欠状態になる
- 目の前がクラクラする
- 呼吸が苦しくなる
このように、貧血で酸欠になると、全身の細胞に栄養が十分に遅れないので、疲れやすくなると言った事が起こる可能性があります。
貧血の改善方法
貧血で、体が疲れやすい人の場合は、まずは、食事で鉄分を補う必要があります。
具体的に鉄分を多く含む食品としては、
- レバー
- ひじき
- あさり
- 赤貝
- 牡蠣
- 大豆
- 大豆製品
- 小松菜
- ほうれん草
- ブロッコリー
- 卵
- バナナ
食事で上記のような鉄分が多い食べ物を摂るようにして、貧血対策を行います。
食事で、貧血の改善対策の効果が出ない場合
食事で鉄分をシッカリと摂っていても、貧血が改善しないで、疲れやすい体質が治らない場合には、病院に行って貧血の原因を調査して、鉄分の薬を貰うと良いです。
もしも、病院に行くのが面倒な場合で、食事療法が難しい場合には、市販の鉄分サプリメントで鉄分を補う必要があります。
⑮更年期障害が原因&改善方法

特に女性の場合は、40代半ばから50代前半になると、閉経を迎えることで、女性ホルモンの「エストロゲン」が減少する事で、体内のホルモンバランスが変わることで、更年期障害になって、急に疲れやすくなる人がいます。
具体的な更年期障害の症状としては、
- 体のほてり(ホットフラッシュ)
- 大量の汗(スウェッティング)
- 胸の痛み
- 脈が速くなる
- 目まい
- 耳鳴り
- 体の冷え
- 抜け毛
- 倦怠感
- 疲れやすい
今までは、更年期とは、女性だけのモノだと思われていましたが、最近では、男性の場合でも40歳ぐらいから更年期になる人もいます。
基本的に、更年期障害になる理由は、ホルモンバランスの乱れです。ホルモンバランスが崩れる事によって起こります。
もしも、40代から50代で、急に疲れやすくなった場合には、更年期障害を疑う必要があります。
更年期障害の治療・改善方法
更年期障害になって、疲れやすい人の場合には、病院に行って医師による治療を受ける必要があります。医師に相談して、納得できない場合には、他の病院を周ると良いです。
実際に、更年期障害の治療を行う場合には、ホルモン注射でのホルモンの補充、漢方薬、低用量のピルを使って、ホルモンバランスを安定させると症状が改善する場合があります。
人によっては、お酒やタバコを控える、運動習慣を持つ、早寝早起きをするち言った様に生活習慣の見直しで症状が改善する場合もあるようです。
⑯妊娠が原因&改善方法

妊娠初期から妊娠8ヶ月の妊婦さんは、体調の変化によって、妊娠前と比較すると疲れやすくなるケースがあります。特に妊娠、7ヶ月ごろの妊婦さんは、特に疲れやすさを感じる人が増えるようです。
実際に、妊婦さんが疲れを感じる原因としては、
- ホルモンバランスが変化する
- 胎児の成長で体型の変化
- お腹が大きくなり血行が悪くなる
- 下半身のむくみ
- 立っているのが辛い
- 大きくなったお腹に圧迫される
- 仰向けで寝るとお腹が苦しい
- 普通に生活していても息苦しくなる
- お腹が出ているので、背中や腰が疲れやすい
妊娠での疲労対策
妊婦さんは、疲れやすいので、基本的に、こまめに休憩を取るよう心掛ける必要があります。さらに、妊娠後期の妊娠8ヶ月や9ヶ月になると、お腹が大きくなるので、同じ姿勢を長時間していると、血流が悪くなり、むくみの原因になります。
この為、長距離、乗り物に乗っているのも良くありません。こまめに休憩を取って、軽い散歩や買い物などで、適度な運動をして、体を動かす事も大切です。
また、胎児に栄養が取られるので、貧血を起こしやすくなるので、疲れや立ちくらみを感じやすくなるので、椅子などで休んで疲れが溜まらないようにすることも大切です。
⑰子供が疲れやすい原因&改善方法

子供と言えば、元気で、動き回って、疲れたらグッスリと寝るので、疲れを溜めると言ったイメージが無いと思います。
しかし、子供でも疲れを溜めて、疲れやすい体質になっている場合があります。
- 何をしても、スグに疲れたと言う
- 学校や習い事を休みたがる
- 食欲がなくなる
また、子供が疲れを感じる原因としては、
- 学校での人間関係に悩んでいる
- 外で気を使い過ぎている
- 友達とのメールのやり取りで気疲れしている
- 嫌な事が続いている
子供が疲れやすい時には、人間関係によって神経的、精神的な疲労がたまっている可能性があります。
食事が子供の疲れやすい原因になる事もある
子供が普段食べている食事内容によっては、「疲れやすい」体質になっている可能性があります。
具体的に、子供が疲れやすい食事としては、
- お菓子
- 白米
- パン
- うどん
- パスタ
- ラーメン
子供に限らす食べた糖類を代謝するためには、ビタミンB群が必要です。この為、たんぱく質や甘いモノばかり食べていると栄養不足になり、疲れやすい体質になります。
子供が疲れやすい対処方法
子供の疲れが何日も続いていたり、食欲もなく元気がない場合には、親や教師などが、子供の異変に気づいてあげる必要があります。子供の変化を注意して見守って、時間を作って話をする必要があります。
食事での栄養バランスが子供の疲れ対策
食事においても栄養バランスを考えた食べ物を意識して、子供に食べさせないと、疲れやすい子供になっている可能性があります。例えば、「ビタミンB群」、「タンパク質」などのような食品を摂る必要があります。
ビタミンB群の効果と必要性
ビタミンB群は、白米やパン、パスタ、うどんなどの糖類の代謝に必要です。ビタミンB群が不足すると、代謝が十分に行えず、栄養不足になって疲れやすくなります。
特に糖質は、血糖値の急上昇をお越し、その後、血糖値が急に下がるので、「低血糖」という症状になるので、糖を補いたくなり甘いモノが食べたくなります。
この悪循環が続くと、精神的に不安定になるので、野菜などからビタミンB群をシッカリと摂る食事を心がけましょう。
※ビタミンB群を含む食べ物
ビタミンB群を含む食べ物としては下記のような食材があります。
豚肉、うなぎ、たらこ、レバー、牛乳、かつお、サンマ、いわし、マグロ、アサリ、牡蠣、ほうれん草、菜の花、納豆、卵
タンパク質の効果と必要性
タンパク質は、人間の体を作るのに重要な栄養成分です。具体的に、タンパク質は、皮膚、爪、内臓などを作るのに必要です。
子供は、昼間に飛んだり、跳ねたりして遊んでいると、目に見えない範囲でも体にはダメージを受けています。また、日に日に身長が伸びていきます。
このように、子供の体を成長させて修復するためには、タンパク質を食事でキチンととって置く事が重要です。
※タンパク質を含む食べ物
タンパク質群を含む食べ物としては、下記のようなモノがあります。
お肉、魚、チーズ、納豆、きな粉、海老、イカ、貝類、牛乳、ヨーグルト
子供が疲れやすい場合のまとめ
子供が、シッカリと睡眠をとらしているのに、疲れやすい体質になっている場合には、「精神面」、「栄養面」と言った2つの点を注意する必要があります。
